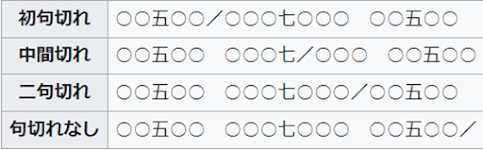卯春興
7-5 鴨のりて氷ながるゝ春日かな
「鴨」(三冬)、「氷」(晩冬)、「氷流る=流氷」(仲春)、「薄氷(春の氷)」(初春)、そして、「春日」(三春)、「初春」(新年)と、この句の主たる季語は、前書の「卯春興」の「春日」の「初春」(新年)の句と解したい。
≪【解説】年の始めをことほいで初春という。旧暦の年の始めは、二十四節気の「立春」のころにあたったので、「初春」と呼んで祝った。新暦に変わって冬に正月を迎えるようになっても、旧暦の名残から年の始を「初春」と呼ぶ。
【実証的見解】二十四節気は太陽暦に基づいて、一年の長さを二十四に分けたもの。その節入を「立春」や「啓蟄」、「秋分」などの言葉で区切る。二十四節気はもともと中国で生まれたもの。中国では、「立春」と立春の次の「雨水」を含む月を正月として年のはじめとし、これが日本にも伝わって、「立春(現在の二月四日ごろ)」を「正月節」、次の雨水を「正月中」というようになった。以下、啓蟄は「二月節」、春分は「二月中」、清明は「三月節」(以下略)である。旧暦は、月の満ち欠けを基本とした暦であるから、二十四節気に先行して月日が移ろうが、行過ぎれば「閏(うるう)月」を設けて月日を後戻りさせ、基本的には二十四節気に添って進行するのである。≫(「きごさい歳時記」)
「山谷堀/今戸橋/慶養寺」(江戸名所図会より)
http://arasan.saloon.jp/rekishi/edomeishozue17.html
≪「待乳(まつち)しづんで、梢(こずえ)のりこむ今戸橋、土手(どて)の合傘(あいがさ)、片身がはりの夕時雨、君をおもへば、あはぬむかしの細布(ほそぬの)
右 英一蝶(はなぶさいっちょう)戯作」
挿絵の手前の川は隅田川でそこに注ぐ川には「今戸堀り」とあり、これが山谷堀です。堀には「今戸橋」が架かっており、その左上には「此辺船宿」とあります。絵の中央が「慶養寺」で「本堂」、「弁天」があります。遠景に「山谷」があります。≫
鎌田の梅見にまかりて
7-6 萬歳を居並て待つ田舎哉
季語は「萬歳=万歳(まんざい)」(新年)
≪【子季語】千秋万歳、万歳楽、御万歳、門万歳、三河万歳、加賀万歳、大和万歳、万歳大夫
【関連季語】才蔵市
【解説】新年を祝う門付けの一つであり、主役の万歳大夫と脇役の才蔵との二人組で行われる。その家が千年も万年も栄えるようにと賀詞をのべる。才蔵の鼓に合わせて舞ったり歌ったり、滑稽な問答を交わしたりする。
【実証的見解】万歳は出身地によって、三河万歳、大和万歳、尾張万歳などと地名を冠して呼ばれる。もともとは室町時代の下層民の千秋(せんず)万歳が起源とされる。主役の万歳太夫は、風折烏帽子に紋服姿で手に扇を持つ。脇役の才蔵は大黒頭巾をかむって鼓を打つ。昔、江戸では、「才蔵市」なるものが立ち、万歳太夫が相方の才蔵をその市で見つけたという。
【例句】
やまざとはまんざい遅し梅の花 芭蕉「真蹟懐紙」
万歳の踏みかためてや京の土 蕪村「落日庵句集」
万歳や門に居ならぶ鳩雀 一茶「七番日記」
万歳や黒き手を出し足を出し 正岡子規「寒山落木」
万歳も乗りたる春の渡かな 夏目漱石「漱石俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)
「蒲田の梅園」(『絵本江戸土産』冊次2)/二世歌川広重画。/嘉永3年(1850)~慶応3年(1867)刊。
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hana/contents/02.html
≪現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園(梅の木を多く植えた庭園)のこと。≫
7-7 はつ午やしるし斗りを揚豆腐
≪【解説】二月の最初の午の日に行われる稲荷神社の祭礼で、午祭ともいう。京都深草の伏見稲荷をはじめ大阪の玉造、愛知県の豊川稲荷、また神戸の摩耶参など、各地の稲荷神社で盛大に行われる。二の午、三の午もある。
【実証的見解】稲荷信仰はもともと農事の神の信仰で、初午はその年の五穀豊穣を願うものであった。農家はこの日、稲荷社にお神酒や油揚げ、初午団子を供えたりした。
【例句】
はつむまに狐のそりし頭哉 芭蕉「末若集」
初午や物種うりに日のあたる 蕪村「蕪村句集」
初午やその家々の袖だゝみ 蕪村「蕪村句集」 ≫(「きごさい歳時記」)
「▲はるばる江戸から大坂の水間寺まで銭を運んできた通し馬。運送馬(駄馬)の腹当には、縁起をかついで「仕合」「吉」「宝」という文字を書くのが通例であった。(小学館『新編日本古典文学全集68 井原西鶴集3』より)
井原西鶴…1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。俳諧では矢数俳諧を得意とした。庶民の生活を写実的に生き生きと描いた浮世草子の名作を多数書き、『好色一代男』『好色五人女』などの好色ものや、経済小説とも言える『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などで知られる。」
http://www.edoshitamachi.com/modules/tinyd11/index.php?id=5
江戸時代、初午(はつうま)の日(2月の初めに巡ってくる午の日。今年は2月5日は縁起がよく、物事を始めるのに良い日だとされた。
初午にかかわるこんな話が、元禄元年〈1688〉年に刊行された井原西鶴(さいかく)の浮世草子(うきよぞうし)『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』の劈頭(へきとう)を飾っている(「初午は乗つてくる仕合(しあわ)せ」)。
初午の日、泉州(せんしゅう。大阪府貝塚市)にある水間寺(みずまでら)は参詣人が多かったが、この寺には古くからのある風習があった。参詣した折に、寺から借銭するとご利益があるというのだ。お寺から3文(もん)、100文と銭を借りたとすると、翌年に借りた倍の6文、200文を返すという習わしであり、信者は決まって「倍返し」したものだった。
ある年の初午の日、年の頃なら23、4歳の質素な身なりをした男が水間寺へやってきて、「借り銭を一貫文(いっかんもん)欲しい」と言った。一貫文とは1両の4分の1、すなわち1000文(実際は960文)である。寺の役人は例のない高額で驚いたが、きっと倍返しをしてくれるだろうからと一貫文を渡したところ、男は借りたまま行方が分からなくなってしまった。
じつはこの男は、江戸の小網町(こあみちょう。中央区日本橋)のはずれで船問屋(ふなどんや)「網屋(あみや)」をしている者であった。水間寺で金を借りて、漁師たちに貸付けようと考えていたのである。江戸に戻った男は、「仕合丸」と書いた引出しに水間寺の銭を入れておき、漁に出る漁師たちに、これは水間寺で借りた縁起がいい金だからと言って貸付けていた。その噂(うわさ)が広がって、漁師たちは100文借りたなら、無事に漁から帰ったら倍の200文を返すという具合に、倍返しが定着した。そして13年目になると、それが積もり積もって、8192貫文(819.2万銭)にまで増えた。
そこで男は、この銭8192貫文を「通し馬」(東海道を江戸から泉州まで同じ馬で運ぶ)で水間寺まで運び、お礼参りをしたのである。
初午の日に借りた1貫文が、13年目におよそ8000倍、当時の換金レートにすると2048両に膨れあがった。ちなみに、これを西鶴は逆に、「借銀(かりがね)の利息程おそろしき物はなし」と慨嘆している。今でもローンの複利計算の利息は「おそろしき物」であろう。
さて、この男は、江戸から大坂まで銭8192貫文を返しに行くのに205頭の馬を連ねて行った。当時、駄馬(だば。荷物を専門に運ぶ馬)1頭に積める荷は40貫(約150㎏。銭は約4万文を積める)と決められているから、銭8192貫文を運ぶには205頭の駄馬が必要となる。
ふつう駄馬は、2里運んで42文、江戸と大坂は130里とされるから、この計算でゆくと、1頭あたり(130里÷2里=65)×42文=2730文(約0.68両)の経費がかかる。帰りの空馬代を合わせて、1頭につき1両ほど運賃がかかったとすると、雇った通し馬205頭なら205両になり、2048両運ぶのに205両の運送費がかかった計算となる。
一方、定飛脚(じょうびきゃく)の江戸為替での送金は手数料が5、6%程度だから、5%で計算しても、2048両×5%=102.5両となり、江戸為替のほうが半分の割安になっていた。
約2倍の経費をかけてまでなぜ馬で運んだと思うだろうが、そこには男の計算があったのである。
つまり、たとえ輸送費が高くついても「網屋」の宣伝になると男は考え、通し馬で東海道をパフォーマンスしながら水間寺に銭を運んだ。そんな宣伝上手のアイディアマンだった故に、この男は、西鶴がいう「親の譲りを受けず、その身才覚にして稼ぎ出し」儲(もう)けて、「武蔵にかくれなし」と、今で言えば首都圏でも有名な富豪になったという。
親譲りの資産がなくても金持ちになれたという例は、現代で言えばIT産業の起業家が莫大(ばくだい)な資産を築いたものに匹敵しよう。
だが、小説のモデルになった「網屋」の栄華も長く続かず、その存在は早く人びとの記憶から消えてしまったと西鶴は結んでいる。ひょっとしたら現代のIT産業で富豪になった場合も、アイディアが続かないと、この男の二の舞になるかも知れない。≫
7-8 芹摘みに出て孫もるす彦も留守
≪【子季語】根白草、根芹、田芹、芹摘む、芹の水
【解説】芹は春の七草の一つで、若菜を摘んで食する。七草粥が代表的だが、ひたし、和え物にしたり香味料として吸い物に用いたりする。
【科学的見解】芹(セリ)は、在来の植物であり、田圃や池付近など湿り気のある場所に生育する。花期は、七月~八月であり、小さな白い花がたくさん集まった花序を形成する。名前は、水辺に群がって「競り(せり)」合うように増え、また花が咲くと草丈を「競り(せり)」合うことに由来する。(藤吉正明記)
【例句】
我がためか鶴はみのこす芹の飯 芭蕉「続深川」
これきりに径尽たり芹の中 蕪村「蕪村俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)
喜多川歌麿「絵本四季花」より『若菜摘み』/寛政13年〈1801年〉/(ボストン美術館蔵)
https://www.benricho.org/koyomi/nanakusa-wakana.html
この句自体では、「芹(摘み)」(三春)の句ということになるが、上記の「若菜摘み」(歌麿画)になると、「若菜摘(わかなつみ)」(新年)そして「子の日遊び」(新年)の光景となってくる。そして、掲出句の、「孫もるす彦も留守」というのは、何か仕掛けのある句のようで、この「彦」は、「山彦」=「山の神」(口やかましくなった女房)などの意が隠されているような雰囲気である。
≪【解説】一月七日の七種の菜を摘むこと。古くから正月はじめての子の日に若菜を摘む習慣があったが、後に、七種に合わせて一月六日の行事になった。
【例句】
畠より頭巾よぶなり若菜つみ 其角「鳥の道」
ととははやす女は声若しなつみ歌 嵐雪「虚栗」
山彦はよその事なりわかな摘 千代女「千代尼句集」 ≫(「きごさい歳時記」)